長年にわたり所有されてきた大切な不動産。しかし、いざ売却を考えたときに、「既存不適格建物」という言葉に直面し、不安を感じている方は少なくないでしょう
「売れないのでは?」「大幅な値下げが必要なのでは?」
ご安心ください。不動産業界で25年間、数多くの物件を見てきた私の結論から申し上げますと、既存不適格建物でも売却は可能です。ただし、一般的な物件と同じ売り方では、買主様との交渉や融資の面で不利になりがちです。
このブログでは、既存不適格建物の売却を成功させるための**具体的なロードマップと、長年の経験から得た「有利に売るための極意」**を惜しみなくお伝えします。不安を解消し、あなたの資産価値を最大限に引き出すための戦略を、一緒に立てていきましょう。
PR 三井のリハウスでスピード無料査定!確かな経験と実績で安心の不動産査定。1. まず理解すべき「既存不適格」の正しい定義
「既存不適格」は「違法建築」ではない
既存不適格建物とは、建てられた時点では合法だったものの、その後の法律(特に建築基準法)の改正や都市計画の変更により、現在の基準には適合しなくなった建物のことです。
- 具体例:
- 改正後に容積率がオーバーしてしまった
- 接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接すること)の基準が厳しくなり、再建築が難しくなった
- 防火・耐火の基準が変わった
これに対し、「違法建築」は、建てられた時点で既に当時の法律に違反していた建物です。
既存不適格建物は、原則としてそのまま使用し続けることは問題ありません。しかし、増改築や建替えには現行法の制限を受けるという点が、売却における最大の課題となります。この違いを明確に理解することが、正しい売却戦略の第一歩です。
買主が抱く2大懸念を把握する
既存不適格建物の売却において、買主様が最も不安に感じる点は以下の2つです。
- 融資(住宅ローン)がつきにくいのではないか?
- 将来、自由に建替えや増改築ができないのではないか?
売却戦略の鍵は、この「不安」を先回りして解消するための**「情報開示」と「専門的な提案」**にあるのです。
2. 売却前の必須準備!既存不適格を資産に変える3つのステップ
既存不適格建物を有利に売却するためには、事前の準備が9割を占めます。ここからがベテランのノウハウです。
ステップ1:建築士による「専門意見書」を取得する
これが最も重要です。単に「既存不適格建物です」と伝えるだけでは買主は及び腰になります。
必ず建築士に依頼し、以下の点を明確にした専門意見書または調査報告書を作成してもらってください。
- 不適格の具体的な理由: (例:容積率が〇〇%超過、接道幅が〇〇cm不足)
- 建替えの可否: 「再建築不可」なのか、「一部は増改築可能」なのかを明記。
- 修繕・維持管理の安全性: 既存建物の耐震性や構造的な安全性を可能な範囲で評価。
この書面は、**「不適格だが、安全面や今後の利用について専門家の見解がある」**という安心感を買主に提供し、契約不適合責任のリスクも軽減します。
ステップ2:正確な情報を徹底的に開示する
既存不適格建物であることを隠蔽したり、曖昧にしたりすることは絶対にいけません。後々の契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に問われるリスクを高めます。
売買契約書や重要事項説明書に、不適格の事実と具体的な内容を明記し、買主様に理解してもらうことが信用につながります。開示が誠実であるほど、買主様も安心して購入に踏み切れます。
ステップ3:融資対策を講じる
一般的な金融機関の住宅ローンは、既存不適格建物、特に再建築不可の物件には消極的になりがちです。
- 地元の信用金庫や第二地銀との連携: 大手銀行よりも、地域の特性や物件の収益性(賃貸として)を評価してくれる金融機関は存在します。
- 「リフォーム一体型ローン」の提案: 不適格を理由に評価額が下がった分、リフォーム費を一体化したプランの方が、買主にとって資金計画が立てやすくなります。
- 不動産会社と連携し、事前に融資相談をシミュレーションしておくことで、買主側の融資特約解除リスクを下げることができます。
3. 誰に売る?ターゲット別の売却戦略
既存不適格建物は、その特性から買主を絞り込むことが成功の鍵となります。
ターゲットA:現況を維持して収益化を狙う「投資家・デベロッパー」
容積率がオーバーしている既存不適格建物は、実はこの層にとって大きなメリットがあります。
- 訴求ポイント: 現行法で建て替えると小さくなってしまう建物が、現況では大きな収益面積を確保できている点。利回り計算で有利になる。
- 戦略: 土地のポテンシャルではなく、**「収益物件」**として提案。利回りや賃貸需要の高さに焦点を当て、一般的な住居用物件とは異なるルート(投資家向けネットワーク)で売却活動を展開します。
ターゲットB:リフォームして住み続ける「リノベーション志向の個人」
再建築不可だからこそ、価格が抑えられているという点を逆手にとります。
- 訴求ポイント: 建物価格が抑えられている分、「リフォームやリノベーション費用」に予算を回せるメリット。
- 戦略: リノベーション専門の工務店と組み、**「リフォーム後の具体的なイメージパースや見積もり」**を提示。特に、古民家再生や個性的な住まいを求める層に響くよう、内装の可能性を最大限にアピールします。
ターゲットC:隣接地の所有者
隣接地の所有者にとって、あなたの既存不適格建物の土地は、「自己の土地の有効活用」につながる最高の資産になり得ます。
- 訴求ポイント: 隣接することで、自身の土地の接道義務を解消できたり、広い敷地として建替えができたりするメリット。
- 戦略: 不動産会社に依頼し、隣接地の所有者へ丁寧に個別に打診を試みる。このルートは、市場価格以上の高値で売却できる可能性を秘めています。
4. 価格交渉と媒介契約の極意
適正価格の設定と値下げ交渉の戦術
既存不適格建物は、適正な市場価格から、不適格によるマイナス要因を冷静に査定して価格をスタートさせるべきです。
- 比較対象を見つけさせない: 既存不適格物件は特殊なため、近隣の「完全な合法物件」と同じ土俵で比較させないことが重要です。その物件固有の価値(立地、日当たり、特殊な構造)を強調します。
- 弱点を先に開示し、価格に織り込み済みと主張: 買主側から「既存不適格建物だから値下げを」と言われる前に、「不適格の分は既に考慮してこの価格です」と主張できるよう、根拠ある価格設定が必要です。
不動産会社との媒介契約
既存不適格建物の売却では、地元の状況や建築法規に精通し、**「融資対策」や「専門的なターゲット戦略」**を立てられる不動産会社を選ぶことが不可欠です。
- 専任媒介契約を選択し、一つの会社に腰を据えて戦略的な販売活動に取り組んでもらうことを推奨します。複数の会社に任せると、単に価格競争に陥り、「既存不適格建物」というネガティブな情報が広がりかねません。
まとめ:既存不適格建物は「欠陥」ではなく「特性」です
既存不適格建物は、決して売れない物件ではありません。それは、現行法規とは異なる**「歴史的特性」**を持った物件と捉えるべきです。
大切なのは、その特性を隠すことなく、**「誰にとって価値があるのか」**を見極めることです。
- 建築士による専門意見書の取得
- 正確な情報開示と融資対策
- 投資家やリノベーション層への的確なターゲティング
この3点を徹底すれば、既存不適格建物でも、必ずその価値を理解し、大切に使ってくれる買主様と巡り合えます。不安を抱えるより、まず一歩踏み出し、経験豊富な不動産会社にご相談ください。25年の知見を活かし、あなたの売却を全力でサポートいたします。
あなたの不動産の可能性を、諦めないでください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
以上、コロコロでした!
PR
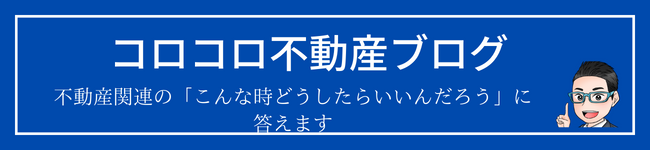

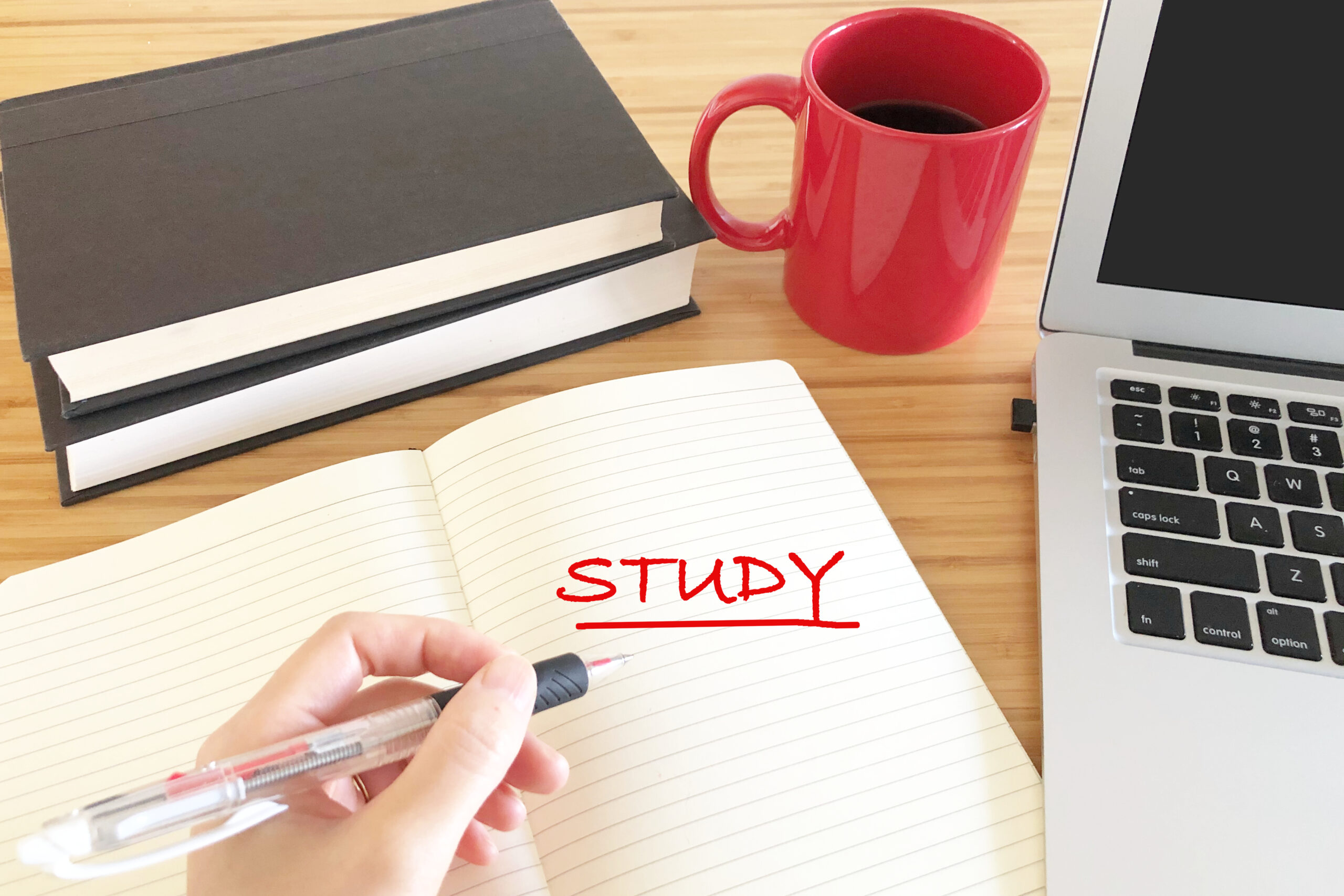


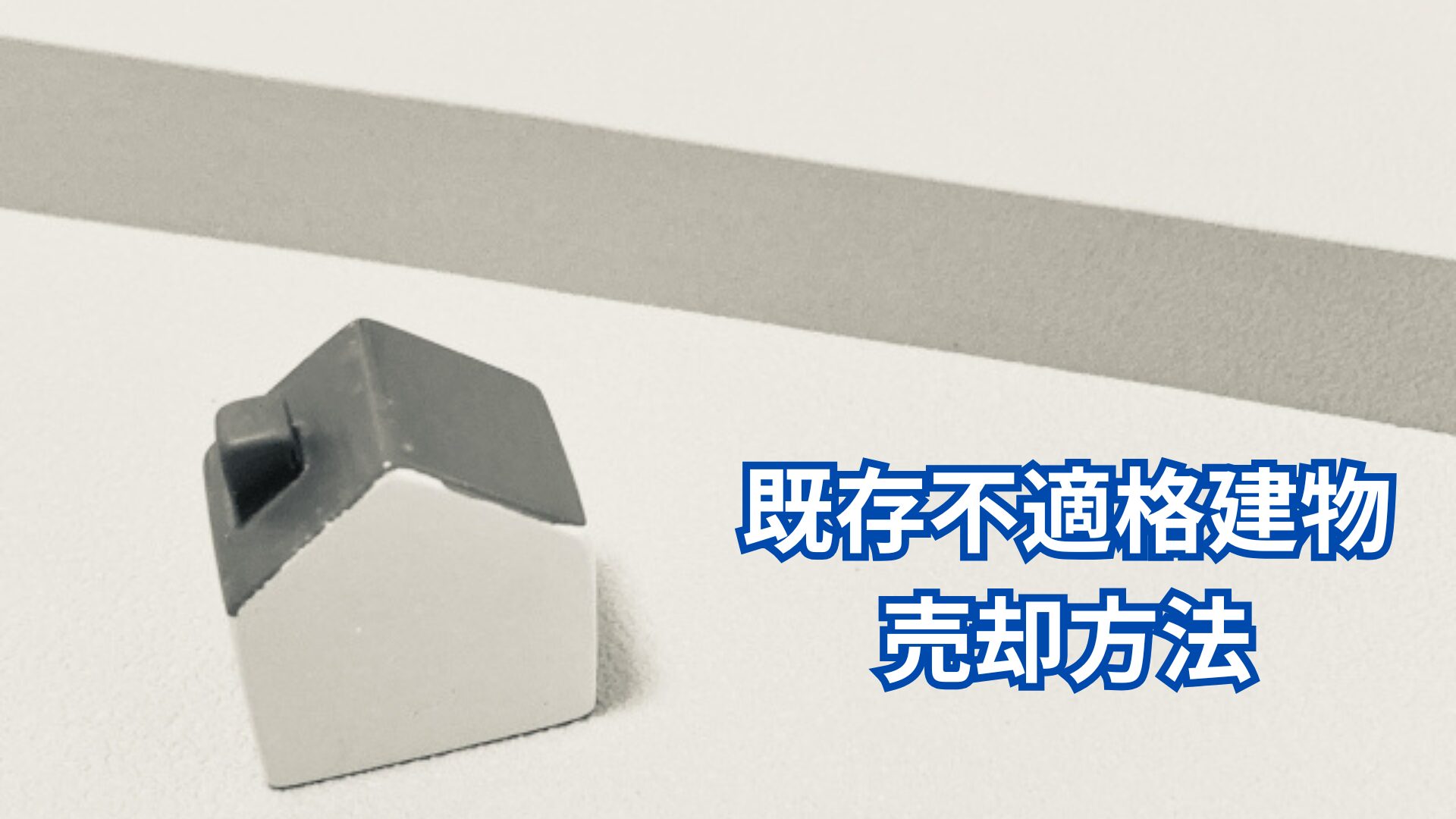



コメント