はじめに:なぜこの違いを知る必要があるのか
土地という高額な資産を売却する際、「面積」は売買価格を決定づける最も重要な要素の一つです。しかし、この「面積」の捉え方には、「公簿(こうぼ)」に基づくものと「実測(じっそく)」に基づくものの2種類があり、どちらを採用するかによって売主様・買主様双方のリスクと得る利益が大きく変わってきます。
私は不動産業界で25年間、数多くの土地取引を仲介してきましたが、この公簿売買と実測売買の違いを理解せずに取引を進め、後でトラブルになるケースを見てきました。特に、これから大切な土地を売却しようと考えている売主様には、ご自身の財産を最大限に活かし、かつスムーズで安全な取引を行うために、この違いとそれぞれのメリット・デメリットを深く理解していただきたいと思います。
本ブログでは、不動産売買のベテランとして、公簿売買と実測売買の基本的な仕組みから、売主様にとっての具体的な影響、そして賢い選択をするためのポイントまで解説します
PR 不動産の売却をご検討なら三井のリハウスで無料査定依頼1.不動産取引における「面積」の基本知識
まず、土地の面積に関して、不動産取引で使われる基本的な用語を整理しましょう。
(1)公簿面積(登記簿面積)
**「公簿面積」とは、法務局に備え付けられている「登記簿(登記事項証明書)」に記載されている面積のことです。一般的に、「登記簿謄本の面積」**とも呼ばれます。
この面積は、土地が造成されたり、地籍調査が行われたりした際に測量されたデータに基づいていますが、その測量が数十年以上前であったり、測量技術が未発達であった時代のままで更新されていないケースも少なくありません。そのため、現在の正確な面積(真の面積)とはズレが生じている可能性があります。
(2)実測面積
**「実測面積」**とは、現在の技術と手法で、専門家である土地家屋調査士が現地を測量して算出した正確な面積のことです。
この測量は、隣接地の所有者との間で**「境界確認」を行い、「境界標」**を設置した上で実施されます。この実測によって得られた面積は、現時点での土地の正確な大きさを反映しており、公簿面積よりも信頼性が高いとされます。
2.「公簿売買」とは?
(1)公簿売買の定義と仕組み
**「公簿売買(こうぼばいばい)」**とは、登記簿に記載されている「公簿面積」を根拠として売買代金を決定し、契約を締結する取引方法です。
例えば、公簿面積が100㎡、単価が坪あたり100万円(約30.3万円/㎡)の場合、代金は「100㎡ × 30.3万円/㎡ = 3,030万円」となります。
(2)売主様にとってのメリット
- 取引の迅速化とコスト削減:
- 測量が不要なため、測量費用(数十万円〜)や測量期間(1ヶ月〜数ヶ月)がかかりません。すぐに売却活動を開始でき、取引完了までの期間も短縮できます。
- 買主側も、公簿面積で納得してくれれば手続きが非常にスムーズです。
- 責任範囲の明確化:
- 万が一、契約後に実測面積が公簿面積よりも小さかったとしても、**売主は代金の返還(精算)義務を負いません。**これが公簿売買の最大の特徴であり、売主様にとってのリスクヘッジとなります。
(3)売主様にとってのデメリットとリスク
- 売却機会の損失(真の価値を活かせない可能性):
- もし実測面積が公簿面積よりも大きかった場合、その**超過分の代金を受け取ることができません。**売主様が本来得るべき利益を逃してしまうことになります。
- 買主の懸念と交渉の難しさ:
- 特に大きな建物(マンションやアパート)を建てたい買主は、面積のズレを非常に嫌がるため、公簿売買では敬遠されることがあります。また、買主から「面積リスク」を理由に単価の値下げ交渉を強く求められる可能性が高まります。
- 将来的なトラブルの種:
- 境界が不明確なままだと、将来的に隣地所有者との間で「境界紛争」が発生するリスクが残ります。
3.「実測売買(精算取引)」とは?
(1)実測売買の定義と仕組み
**「実測売買(じっそくばいばい)」**とは、事前に(または契約後に)土地家屋調査士による実測を行い、その「実測面積」を基に最終的な売買代金を確定・精算する取引方法です。
一般的には、まず公簿面積を基にした「概算代金」で契約を結び、後日確定した実測面積を基に「最終代金」を算出し、差額を清算(返金または追徴)します。このため、「清算取引」とも呼ばれます。
(2)売主様にとってのメリット
- 土地の真の価値を反映:
- 実測の結果、**公簿面積よりも実測面積が大きかった場合、その超過分も含めた代金を受け取ることができます。**売主様にとっては、土地の持つ真の価値を最大限に活かせます。
- 買主の安心感と購買意欲の向上:
- 正確な境界と面積が確定していることで、買主は安心して取引に臨めます。特に、住宅メーカーやデベロッパーなどのプロの買主は、実測売買を好みます。結果として、買主が見つかりやすくなり、より高い価格での売却が期待できます。
- 将来的なトラブル防止:
- 売却前に境界を確定し、**「境界確認書」**を作成するため、売却後に隣地との境界紛争が発生するリスクを未然に防げます。
(3)売主様にとってのデメリットとリスク
- 測量費用と時間:
- 売主様が測量費用を負担する必要があり、また測量完了までの売却期間が延びることになります。
- 代金減額のリスク(精算リスク):
- もし実測面積が公簿面積よりも小さかった場合、差額を算出して買主に返金(代金が減額)する義務が生じます。売却代金が当初の想定より下回る可能性があります。
4.ベテランが教える!賢い選択をするための3つのポイント
公簿売買と実測売買、どちらを選択すべきかは、土地の状況や売主様の意向によって変わります。25年の経験から、判断の際に考慮すべき重要なポイントを3つお伝えします。
ポイント1:公簿面積と実測面積の「ズレ」の可能性を探る
- 古い登記や測量: 昭和初期や戦前など、登記簿に記載されている測量年代が古い場合は、公簿面積と実測面積のズレが大きい可能性が非常に高いです。
- 地形の複雑さ: 土地が複雑な形状をしている場合や、過去に**分筆(土地を分けること)や合筆(土地を合わせること)**が行われている場合も、ズレが生じている可能性が高いです。
- 境界標の有無: 現地に**「境界標」(コンクリート杭や金属プレートなど)が全く見当たらない**場合は、境界が不明確であるため、実測の必要性が高いと言えます。
これらの状況に該当する場合は、実測面積が公簿面積よりも大きい可能性も十分あります。その場合、公簿売買で売ってしまうと、売主様は大きな損をしてしまうことになります。
ポイント2:買主のニーズを見極める
- 個人(自宅建築)の買主: 一般的な個人の方が、すでに建物の計画がある場合、面積のズレにそこまで神経質にならないこともあります。
- プロの買主(業者): 不動産業者や建売業者は、将来の転売や事業計画を正確に進めるため、実測売買を強く求めます。この層をターゲットにするなら、実測売買は必須と考えた方が良いでしょう。
ポイント3:費用対効果を冷静に判断する
- 単価が高いエリア: 土地の単価(平米単価)が高い都心部などでは、わずか数㎡のズレでも代金の差額が数百万円になる可能性があります。このようなエリアでは、測量費用をかけてでも実測売買を行う方が、最終的な手取り額が増える可能性が高く賢明です。
- 売却期間の優先度: 「とにかく早く現金化したい」という意向が強い場合は、測量期間が不要な公簿売買も選択肢に入ります。ただし、価格交渉で不利になるリスクは覚悟しましょう。
5.売主様が取るべき行動:まずは「仲介業者」にご相談を
公簿売買と実測売買のどちらを選択するかは、非常に重要な初期判断です。
まずは、信頼できる不動産仲介業者に相談し、過去の取引事例や周辺の相場、そしてご自身の土地の状況(登記簿の古さ、地形など)を総合的に分析してもらいましょう。特に、**「公簿面積と実測面積がどれくらいズレている可能性があるか」**について、ベテランの知見を借りて推測してもらうことが重要です。
場合によっては、契約前の測量を仲介業者が提案したり、測量費用を売買契約の特約で調整したりするなど、売主様にとって最善となるようサポートしてくれるはずです。
PR 不動産の売却をご検討なら三井のリハウスで無料査定依頼まとめ
土地売却における公簿売買と実測売買は、それぞれ「スピード・コスト」と「正確性・最高額」のトレードオフの関係にあります。
- 公簿売買: 手間をかけず、早く売りたい場合に適していますが、売却額が本来の価値を下回るリスクがあります。
- 実測売買: 土地の真の価値で売りたい、将来のトラブルリスクをゼロにしたい場合に適していますが、測量費用と時間が必要です。
あなたの土地を最も良い条件で、そして安全に売却するために、この違いを理解し、最良の選択をしてください。
あなたの土地売却が成功することを心から願っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
以上、コロコロでした!
PR
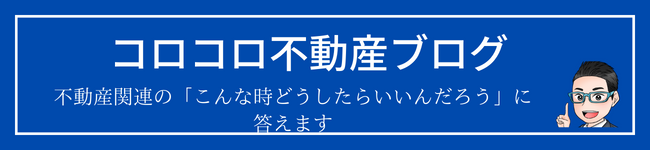

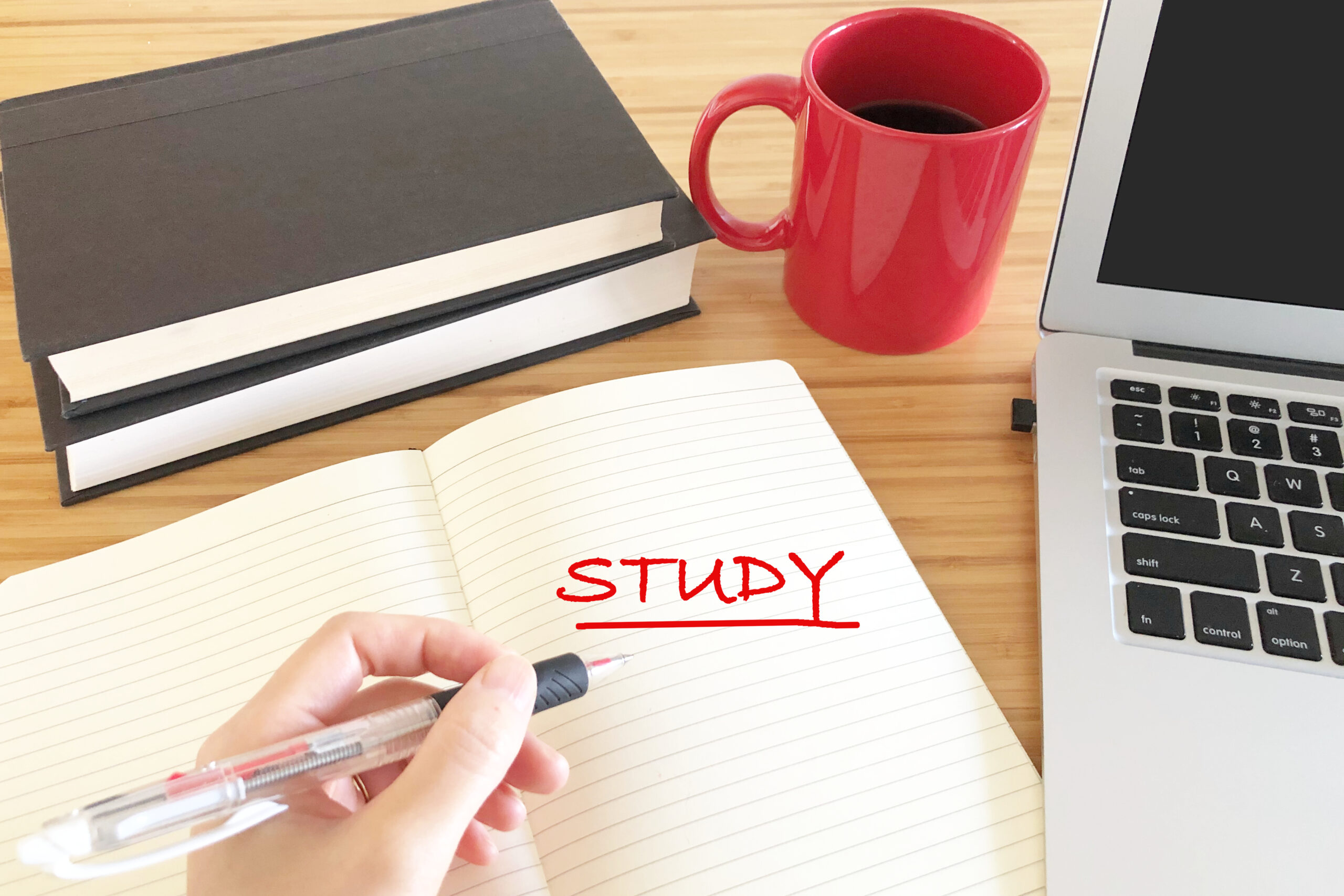






コメント